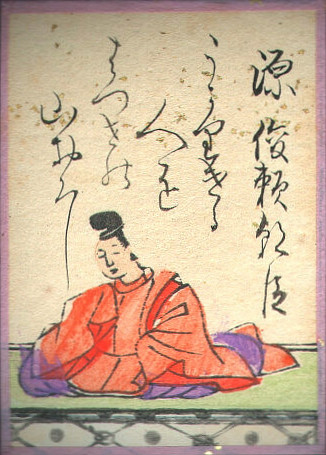
うかりける 人をはつせの 山下風
はげしかれとは いのらぬ物を
| う | |
| 憂かり | ける |
| 形ク | 助動 |
| 「憂し」 (連用形) |
過去 (連体形) |
| ひと | |||
| 人 | を | はつせ | の |
| 名 | 格助 | 【掛詞】 | 格助 |
| ①名「初瀬」。奈良県桜井市の地名。 + ②動「果つ」。終わる。 |
| やまおろし |
| 山下風 |
| 名 |
| 山颪。 山から吹きおろす激しい風。 |
| はげ | ||
| 激しかれ | と | は |
| 形シク | 格助 | 係助 |
| 「激し」 (命令形) |
| いの | ||
| 祈ら | ぬ | ものを |
| 動 | 助動 | 終助 |
| ラ四 (未然形) |
打消 (連体形) |
感動 |
(私の恋が通じず)つらかったあの人を
(どうにか想いが通じるように)初瀬の(長谷寺の)観音様に祈ったのに、恋は終わってしまった。
その初瀬の山颪よ、
激しくなれとは
祈っていないのになあ。
(=あの人が私につらく当たるようには祈っていないのになあ。)
出典『千載集』恋2・708
色々な要素が複雑に詠み込まれており、現代語訳しにくい歌だ。
何が詠み込まれているかというと、
という物語性をもった歌である。
藤原定家はこの歌を「巧緻な風体で、なかなか真似ができない」と高く評価していた。
初瀬の長谷寺のご本尊として、十一面観音が古来有名です。
観音は救済の菩薩として信仰されてきました。
長谷寺の十一面観音像は女性達の篤い信仰を集めており、恋の救済を求めに来る人も多かったのです。
源俊頼朝臣(1055 - 1129)
源経信(☞71番 夕されば~ の作者)の三男。 俊恵の父。
官職には恵まれなかったが、篳篥(和楽器)や和歌に優れていた。『金葉集』の撰者の一人。
『金葉集』以下の勅撰集に約200首入集。『金葉集』(35首)、『千載集』(52首)ではそれぞれ最多入集している歌人である。
 百人一首 (角川ソフィア文庫)
百人一首 (角川ソフィア文庫)