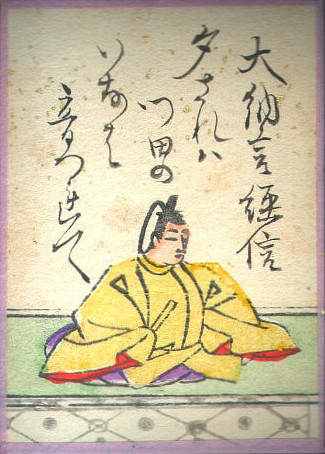
夕されば 門田の稲葉 おとづれて
あしのまろやに 秋風ぞ吹く
| ゆふ | ||
| 夕 | され | ば |
| 名 | 動 | 接助 |
| ラ四 (已然形) 到来する。 |
順接確定条件 |
| かどた | いなば | |
| 門田 | の | 稲葉 |
| 名 | 格助 | 名 |
| 門前の田。 |
| おとづれ | て |
| 動 | 接助 |
| ラ下二 (連用形) |
| あし | |||
| 蘆 | の | まろや | に |
| 名 | 格助 | 名 | 格助 |
| 田舎家。 |
| あきかぜ | ふ | |
| 秋風 | ぞ | 吹く |
| 名 | 係助 | 動 |
| 強意 | カ四 (連体形) ※「ぞ」の結び |
夕方になると
門前の田んぼの稲の葉を
音を立てて、
蘆ぶきの田舎家に
秋風がやって来て吹くことだ。
出典『金葉集』秋・183
掛詞などの技巧を特に用いず、伸び伸びと秋の風情を詠み上げた叙景歌だ。
詞書きによると、梅津(現在の京都市右京区)にある源師賢の山荘で詠まれた。
同じく秋の情景を詠み上げた、1つ前の70番歌「☞寂しさに 宿を立ち出でて 詠むれば いづくも同じ 秋の夕暮れ」(良暹法師)と対比してみよう。
印象が随分違うことが分かる。
| 70 さびしさに | 71 ゆふされば | |
|---|---|---|
| 場所 | 自分の庵。 本当に寂しいところ。 |
源師賢の山荘。 立派な別荘だったという。 |
眼前の 光景 |
寂しい秋の夕暮れ。 | 門前の(たわわに実った)田んぼ。 | 表現 | 「秋の夕暮れ」 新しい表現。万葉集に無く、勅撰集で初出。 |
「夕されば」 古い表現。万葉集でも多く登場している。 |
このように、
70番「さびしさに」 → 寂しげで感傷的・新しい表現の歌。
71番「夕されば」 → 豊かな秋の光景・古い表現の歌。
と対照的である。
大納言経信(1016 - 1097)
源俊頼(☞74番 うかりける〜 の作者)の父。
1094年から、大宰権の帥に任命されて大宰府へ下り、任地で没。
和歌・管弦に秀でており、藤原公任と並んで多才と評価されていた。
『後拾遺集』以下、勅撰集に86首入集。
 百人一首 (角川ソフィア文庫)
百人一首 (角川ソフィア文庫)