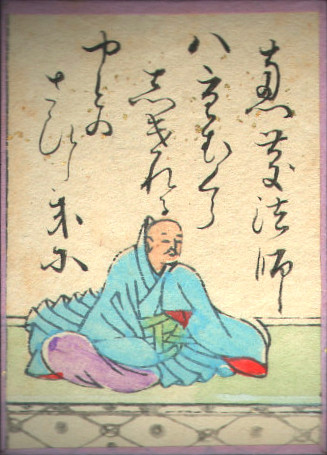
やへ葎 しげれる宿の さびしきに
人こそ見えね あきは来にけり
| やへむぐら |
| 八重葎 |
| 名 |
| 蔓性の雑草。 |
| しげ | やど | ||
| 繁れ | る | 宿 | の |
| 動 | 助動 | 名 | 格助 |
| ラ四 (已然形) |
存続 (連体形) |
同格 |
| さび | |
| 寂しき | に |
| 形シク | 格助 |
| (連体形) |
| ひと | み | ||
| 人 | こそ | 見え | ね |
| 名 | 係助 | 動 | 助動 |
| 強意 | ヤ下二 (未然形) |
打消 「こそ」の結び(已然形) |
| あき | き | |||
| 秋 | は | 来 | に | けり |
| 名 | 係助 | 動 | 助動 | 助動 |
| カ変 (連用形) |
完了 (連用形) |
詠嘆 (終止形) |
葎が幾重にも
生い茂っている
寂しい宿に
人は誰もやって来ないけれど、
秋はやって来たなあ。
第二句の最後の格助詞「の」は、同格の「の」だ。
現代語でいうと、「で」。下にも同じ語に修飾する語が続く。
八重葎しげれる宿のさびしきに
の場合、「宿」に修飾する語がその後に続いている。
八重葎が茂っている宿で、寂しい(宿)に
ということ。
出典『拾遺集』秋・140
・葎がぼうぼうと生えている
・人が誰もやって来ない
・秋のおとずれ
の3重の寂しさを詠み上げた歌である。
この歌の要となるのは『人こそ見えね』の1句だ。
人間は誰もやって来ないが、自然の秋はちゃんとやって来る、という対比が深い感慨とともに詠われている。
詞書によると、河原院にて詠まれた歌。
河原院といえば河原左大臣こと源融(☞『14番 みちのくの』の作者)の邸宅であったが、左大臣の没後は荒れ果ててしまった。
当時は恵慶が親しくしていた安法法師が住んでおり、河原院によく出入りしていたようだ。
恵慶法師(生没年未詳)
『拾遺集』時代、980年〜1000年頃に活躍。
源重之・紀時文・平兼盛などとも親交があり、特に安法法師の住む河原院に集まる歌人達とよく交流していた。
勅撰集には56首入修している。
 百人一首 (角川ソフィア文庫)
百人一首 (角川ソフィア文庫)