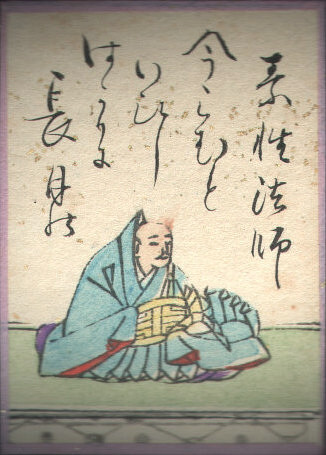
今こむと いひしばかりに 長月の
有明の月を まちいでつるかな
| いま | こ | ||
| 今 | 来 | む | と |
| 副 | 動 | 助動 | 格助 |
| カ変 (未然形) |
意志 (終止形) |
| い | |||
| 言ひ | し | ばかり | に |
| 動 | 助動 | 副助 | 格助 |
| ハ四 (連用形) |
過去 (連体形) |
限定 |
| ながつき | |
| 長月 | の |
| 名 | 格助 |
| 【旧暦9月】 |
| ありあけ | |||
| 有明 | の | 月 | を |
| 名 | 格助 | 名 | 格助 |
| 夜更けに出ている月(月齢20日頃) | |||
| ま | い | ||
| 待ち | 出で | つる | かな |
| 動 | 動 | 助動 | 終助 |
| タ四 (連用形) |
ダ下二 (連用形) |
完了 (連体形) |
詠嘆 |
やがて行こうと
(あなたが)言ったばっかりに、
(それを当てにして毎晩待っているうちに秋も更けてしまい)
旧暦9月の有明の月(が出るの)を
待ち明かしてしまったよ。
出典『古今和歌集』恋4・691
「今来むと」というのは、(あなたが)「やがてやって来る」という意味なので、この歌は待っている側(=女)の立場で詠まれたということになる。
待っていた期間については
①「一晩待っているうちに、有明の月が出てきた」という説
②「月単位で待っているうちに、有明の月が出る日になってしまった」という説
の2つの説があるが、定説は②。
今こむといひし人を、月来待つ程に、秋も暮れ、月さへ在明になりぬとぞよみ侍りけん。こよひばかりは猶ほ心づくしならずや。
撰者とされる藤原定家は②のように、ただ一晩だけではなく何日も待ち明かしたのだと解釈した上で、この歌を「心づくし(感傷的で風韻に富む)」と評価している。
素性法師(生没年未詳)
僧正遍昭(☞12番 あまつかぜの作者)の子。三十六歌仙の一人。
父の薦めで兄の由性とともに出家し、雲林院に住んでいた。宇多天皇の気に入られ、歌合わせにしばしば招かれた。
 百人一首 (角川ソフィア文庫)
百人一首 (角川ソフィア文庫)