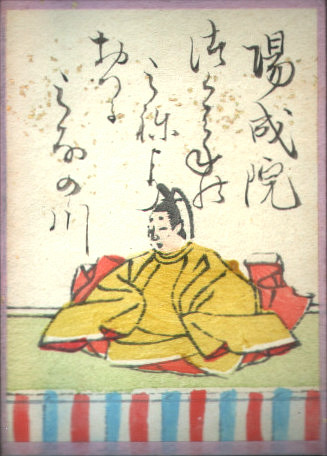
つくばねの 峰より落る みなの川
こひぞつもりて 淵となりぬる
| つくばね | の |
| 名 | 格助 |
| 【筑波嶺】 |
| みね | お | |
| 峰 | より | 落(つ)る |
| 名 | 格助 | 動 |
| タ上二 (連体形) |
| みなの川 |
| 名 |
| 【水無乃川/男女川】 |
| こひ | ぞ | つもり | て |
| 名 | 係助 | 動 | 接助 |
| 【恋】 | 強意 | ラ四 (連用形) |
| ふち | |||
| 淵 | と | なり | ぬる |
| 名 | 格助 | 動 | 助動 |
| ラ四 (連用形) |
完了 「ぞ」の結び(連体形) |
筑波嶺の
峰から(流れ)落ちる
水無乃川(が積もり積もって淵となるように)
この恋も積もり積もって
(深い想いの)淵になってしまったよ。
つくばねの 峰より落る〜
の「ね」は「嶺」、つまり山の頂上・峰のこと。そのあとにまた「峰」ときている。このように、同じ意味の言葉を重ねて詠むことを重詞という。
出典『後撰集』恋3・776
綏子内親王(光孝天皇の皇女)に対する恋を詠った歌で、ほのかに思い初めた気持ちがどんどん積もっていくさまを、僅かな水が積もってできた川の淵にたとえている。
上の句の自然の景色から、下の句の恋の気持ちの表現へ一気に移している。とても鮮やかだ。
ところで、当時の天皇は基本的に平安京(京都)にいたので、筑波山(茨城)を見ることはまず無かった。
歌枕として、幻想の中の存在でしかなかったのだ。
そういうわけで、「峰」(見ね)という言葉と、重詞でのセットになるようになった。
実景を元にした表現ではなく、むしろ想像の中での雄大な光景、というイメージだろうか。
陽成院 (868-949)
名は貞明。清和天皇の皇子で、第57代天皇(在位878-884)。元良親王の父。
幼時から乱行が絶えず、宮中での殺人事件に関与した疑いによりわずか17歳で退位した。乱行の原因は脳病だったという説もある。
陽成院の和歌は、勅撰和歌集には1首しか登場せず、当時あまり注目されては来なかった歌人であったが、それにも拘わらず百人一首に選び出されたのは、元良親王(☞20番 わびぬれば の作者)の父であったからであろう。百人一首は、親子で一緒に選ばれているケースが多く、実に18組(36首)に及ぶ。
 平安朝 皇位継承の闇
平安朝 皇位継承の闇