昔、延長のころ、
その絵妙なるを
「生を殺し
となん。その絵と俳諧とともに
ひととせ病にかかりて、七日を経てたちまちに眼を閉ぢ息絶てむなしくなりぬ。徒弟友どちあつまりて嘆き惜しみけるが、ただ心頭のあたりの少し暖かなるにぞ、もしやと居めぐりてまもりつも三日を経にけるに、手足すこし動き出づるやうなりしが、たちまちため息を吐きて、眼をひらき、醒めたるがごとくに起あがりて、人々にむかひ、
「我、
衆弟らいふ。
「師、三日
興義
「誰にもあれ一人、檀家の平の助の殿の
といふ。使ひ
興義枕をあげて路次の
「君試みに我がいふ事を聞せたまへ。かの漁父文四に魚をあつらへたまふ事ありや。」
助驚きて、
「まことにさる事あり。いかにしてしらせたまふや。」
興義、
「かの漁父三尺あまりの魚を籠に入て君が門に入る。君は賢弟と南面の所に碁を囲みておはす。掃守傍に侍りて、桃の実の大なるを
といふに、助の人々この事を聞きて、あるひは
「我この頃病にくるしみて堪へがたきあまり、その死したるをもしらず、熱き心地すこし冷まさんものをと、杖に
『師のねがふ事いとやすし。待たせたまへ』
とて、
『
といひて去りて見えずなりぬ。不思議のあまりにおのが身をかへり見れば、いつのまに
まづ長等の山おろし、立ちゐる浪に身をのせて、志賀の
『我は仏の御弟子なり。しばし食を求め得ずとも、なぞもあさましく魚の餌を飲むべき』
とてそこを去る。しばしありて飢ますます甚しければ、かさねて思ふに、
『今は堪へがたし。たとへ此の餌を飲むとも
とて遂に餌をのむ。文四はやく糸を収めて我を捕ふ。
『こはいかにするぞ』
と叫びぬれども、他かつて聞かず顏にもてなして、縄をもて我が
『
と
『仏弟子を害する
と
とかたる。
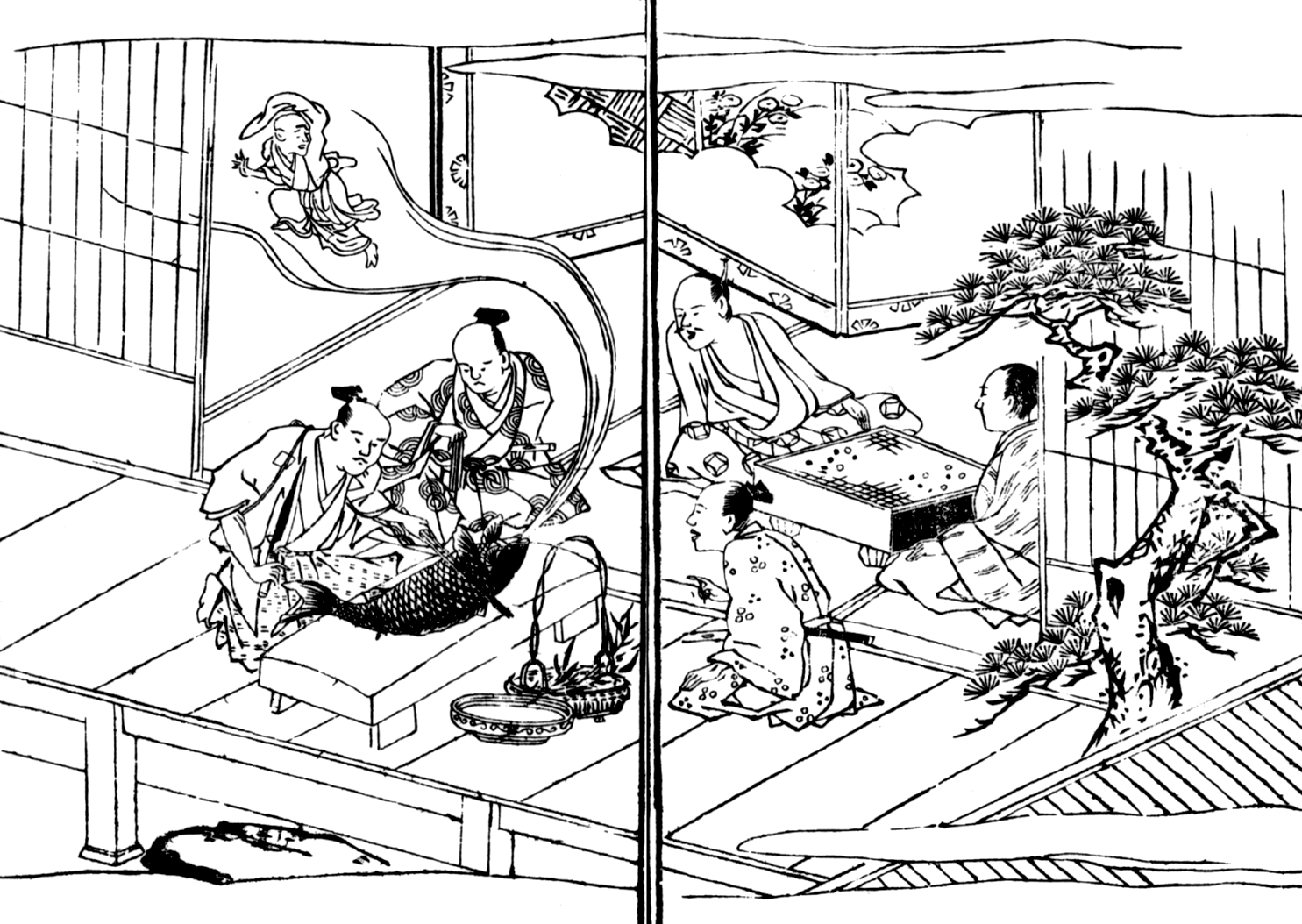
人々大いに感で異しみ、
「師が物がたりにつきて思ふに、其の度ごとに魚の口の動くを見れど、更に声を出す事なし。かゝる事まのあたりに見しこそいと不思議なれ。」
とて、
興義これより病癒えて
昔、延長(西暦923年〜931年)のころ、三井寺に興義という僧がいた。絵が上手なのをもって名人だと世間で評判であった。彼が常々描いていたのは、ふつうの画家のように仏像・山水・花鳥を主とはしていなかった。寺の務めの暇がある日には、湖(琵琶湖)に小舟を浮かべ、網引釣りをしている漁師に金銭をやって、捕れた魚をもとの湖にかえして、その魚が泳ぎ回るのを見てはそれを描いていたので、年月を経て(魚の絵を描く技術は)精細巧妙の域に達した。あるとき、絵のことに思いを凝らして心が憑かれ、思わず眠気をもよおしたので、まどろんでいるうちに夢の中で自分が湖水の中に入って大小の魚と一緒に遊ぶのを見た。目が覚めたので、すぐに(夢で)見たとおりの様子を描いて壁に貼り、自分で「夢応の鯉魚」と名付けた。
その絵がとても優れているのに感心して、(興義の絵を)欲しがる者が殺到したので、(興義は)花鳥・山水の絵を求める者にはただ描き与えたが、鯉の絵だけは一途に惜しんで与えず、誰に向かっても冗談っぽくこう言うのだった。
「(仏教で禁じられている)殺生をして鮮魚を食べている世俗の方には、法師(=私)が養っている魚を決して差し上げられない。」
と。この絵と冗談は、ともに世間の話題となった。
(興義が)ある年病気になって、七日経って突然目を閉じると息が止まって亡くなってしまった。弟子や友達が集まって嘆き悲しんだが、ただ胸の辺りが少し暖かいのに、「もしや(生き返るのでは)」と取り巻いて見守りながら三日過ごしたところ、手足が少し動き出すようになったと思うと、すぐにため息をついて、目を開いて、眠りから覚めたように起き上がって、人々に向かって言った。
「私はずいぶん人間界のことを忘れていた(=正気を失っていた)。何日が経ったのだろうか。」
弟子達は言った。
「法師様は三日前にお亡くなりになった。寺中の人々をはじめ、普段から親しくしている方々もいらして葬儀のことも相談なさったけれど、ただ法師様の胸が暖かいのを見て、棺にも納めずにこのように見守り申し上げていたところ、たった今生き返りなさったところなので、『よくぞ葬儀してしまわなかったことだよ』と喜び合っているところでした。」
興義はうなずいて言った。
「だれでもよいから、檀家の平の助の殿のお屋敷へ参上して申し上げなさい。『興義が不思議なことに生きていました。殿はいま酒を酌み、新鮮ななます(和え物)を作らせなさっているでしょう。少しの間その宴をやめて寺へいらっしゃってください。世にも稀な物語を申し上げたい。』こう言って、先方の人々の様子を見なさい。私が言ったことに少しも違いあるまい。」
と。使いに立った者は不思議に思いながら、(平の助の)屋敷へ行って、興義からの言づてを伝え、人々の様子を窺い見ると、主人の助をはじめ、弟の十郎、家臣の掃守などが輪になって酒を酌み交わしているではないか。法師の言葉どおりなのを(使いの者は)不思議に思った。屋敷の人々もまた、このことを聞いて大いに不思議がり、(平の助たちは)まず箸を置いて十郎と掃守も引き連れて寺へやって来た。
興義は枕から頭を上げてはるばるやって来てくれたことの礼をいったところ、助も(興義が)生き返ったことのお祝いをいった。興義がまず(助に)聞いていった。
「殿、ためしに私の言うことをお聞きください。(あなたは)あの漁師の文四に魚を注文なさったことがあるのではないか。」
助は驚いて、
「たしかにそういうことがあった。どうしてご存知なのか。」
興義は応えて言った。
「あの漁師が3尺(=約90cm)の魚を籠に入れて、あなたの屋敷に入ったでしょう。殿はそのとき、弟君と表座敷で碁を囲んでいらっしゃった。掃守がそのそばに座って、大きな桃を食べながら碁の勝負を観戦していた。漁師が大きな魚を持ってきたのを喜んで、高坏に盛った桃を与えて、さらに杯を与えてお酒を3杯(=たくさん)飲ませなさった。料理人は得意顔で魚をとり、なますにした。ここまで、法師(=私、興義)のいうことに間違いはないでしょう。」
というと、助の家の人々はこのことを聞いて、ある者は不思議に思い、ある物は困惑して、(興義が)このように詳しく語るその理由をしきりに尋ねるので、興義はこう語った。
「わたしはこの頃病気に苦しんで耐え難いあまり、自分が死んでしまったのも知らず、熱があるのを少し冷ましたいものだと、杖に寄りかかりながら門を出たところ、病気のことも忘れたようで、籠の鳥が大空へ帰るような(すがすがしい)気持ちがした。山となく里となく行き進んで、いつものとおり琵琶湖の畔へ出た。水の色が青く美しいのを見ていると、夢見心地で、水浴びして遊ぼうと思って、そこに服を脱ぎ捨てて、身を躍らせて深いところへ飛び込んであちこちと泳ぎ回ったが、子供の頃から泳ぎになれているわけでもないのに、思うがままに(水中で)遊んだ。今思うと思慮のない夢心地だったのだ。しかし人が水に浮かんでいるのは、魚が(水中で泳いで)気持ちがよいことには及ばない。ここでさらに私の中に魚の泳ぎ遊ぶのを羨む気持ちが起こった。そのとき、そばに大きな魚がいて言った。
『法師の願い事はとても簡単なことだ。お待ちください』
といって、はるか水底へ去っていったと思うと、しばらくして、冠や装束で身を包んだ人が、さきほどの魚にまたがって、たくさんの魚たちを連れて浮かんできて、私に向かって言った。
『海の神のご命令があった。老僧(=興義)はかねてから捕らえられた生き物を放すことで功徳が多い。今、(興義は)水中に入って魚の遊びをしたいと願っている。少しの間だけ金の鯉の服を授けて水中の世界を巡る楽しみを味わわせてあげましょう。ただし、餌が香ばしいのにくらまされて、釣りの糸にかかって身を滅ぼさないように』
と言って去って行き見えなくなってしまった。不思議なあまり、自分の身体を顧みると、いつのまにか鱗と金色の光備えた一匹の鯉になっていた。奇妙なことだとも思わず、尾を振ってひれを動かして、思うままに気ままに泳ぎ回った。
まずは長等山の山おろしに吹かれて立ち騒ぐ波に身を乗せて、志賀の浦の渚に泳いでいくと、徒歩でゆく人が着物の裾を濡らす(ほど水面近くで)行き交うのに驚かされて、比良の高い山影が映る深い水底に潜ろうとするも、隠れがたく、堅田の漁り火に引き寄せられるのは夢のようだった。真っ暗闇の夜中の湖上に映る月は、鏡山の峰に鑑のように澄みわたり、たくさんの港をくまなく照らして趣深い。沖の島から竹生島へ泳いでいくときに波に映る丹塗りの垣には実にびっくりした。そうしているうちに伊吹山から吹き下ろす風に、朝妻の渡り船もこぎ出したので、いつの間にか葦の間で眠っていたのを覚まされ、矢橋の渡し船の船頭があやつる水なれ棹から身をかわし、瀬田の橋守りに何度か追い立てられたりもした。日ざしが暖かなときは水の上に浮かび、風がひどいときは深い水底で遊んだ。
(そうしているうちに)急に空腹で食べ物がほしくなり、あちこち探すが手に入れられず狂ったようになっていたところ、突然文四が釣り糸を垂れているところに行き当たった。その餌はとても香ばしい。また、心に海神の戒めを忘れずに思った。
『私は仏の御弟子だ。少々食べ物を手に入れられなくとも、どうしていやしく魚の餌を食べることができようか。(いや、そんなことはできない)』
と思ってそこを去った。しばらくして飢えがますますひどくなってきたので、再び思うことには、
『もう今は耐えがたい。たとえこの餌を食べたとしても、愚かに捕らえられることはあるまい。もともと文四のことは知っているのだから、何をためらうことがあろうか』
と思って、ついに餌を食べた。文四は素早く糸を引いて私を捕まえた。
『これはいったい何をするんだ』
と叫んだけれど、文四は聞こえない様子で(私を)つかみ、縄で(私の)エラを貫き、葦の生えた岸辺に船を繋ぎ止め、私を籠に押し入れて、殿のお屋敷の門へ進んで入った。平の助は弟ぎみと碁の勝負をして楽しんでいらっしゃった。掃守がそばに座って果物を食べている。文四が持ってきた大きな魚を見て、人々はおおいに褒めなさった。私はそのとき人々へ向かって、声を張り上げて
『あなたたちは興義のことを忘れなさったのか。お許しになってください。寺へお返しになってください。』
と何度も叫んだけれど、人々はなにも知らぬ様子であしらい、ただ手をたたいて喜びなさる。料理人はまず私の両眼を左手の指で強くつかみ、右手に研ぎ澄ませた刀を取って、まな板の飢えにのせて今にも斬りかかったとき、私は苦しさのあまり大声を上げて
『仏弟子を殺すなんてことがあるものか。私を助けてくれ、助けてくれ』
と泣き叫んだのだが、聞き入れてくれない。ついに切られると思ったところで夢が覚めた。」
という。
人々は、大いに感動し不思議に思って、
「法師様の物語について考えてみると、そのたび(=法師様が口をきくたび)に魚の口が動くのを見たけれど、とくに声を出すことはなかった。こんなことを目の当たりに見たことは、とても不思議なことだなあ。」
といって、使いを家に走らせて、残っていたなますを湖に捨てさせた。
興義はこれ以降病気が治って、ずっと経ってから寿命を全うして亡くなった。その亡くなった際に、(興義が)描いた鯉の絵数枚を取って湖に散らしたところ、描いた魚が紙から抜け出して水の中を泳いでいってしまった。このために、興義の絵は後世に残らなかった。興義の弟子の成光という者が、興義の神懸かった技を受け継いで名を馳せた。(成光が)閑院内裏の障子に鶏の絵を描いたところ、生きた鶏がこの絵を見て(本物だと思って)蹴ったということが、古い物語(=古今著聞集)に載っている。
江戸時代中期、西暦1776年に出版された、
全9話の短編小説集であり、いずれも日本・中国の古典を下敷きにした作品となっている。現代でいうと、「怪異時代小説」といったところだろうか。
「夢応の鯉魚」は4番目に納められており、中国の「太平広記」(
わかりにくいですが掛詞です。
かくれ
法師様が出てくる仏教説話としてよくある、戒め的なお話。
人々が喜んで食べている魚だが、釣り上げられる魚にとっては非常に恐ろしい思いをして殺されるのであり、殺生の罪を説いたストーリーだ。
いっぽうで、魚として自由に泳ぎ回る活き活きとした描写が鮮やかな作品でもある。とくに「まづ長等の山おろし、立ちゐる浪に身をのせて〜」の部分は、読者を見事に魚の視点に引き込んでいる。