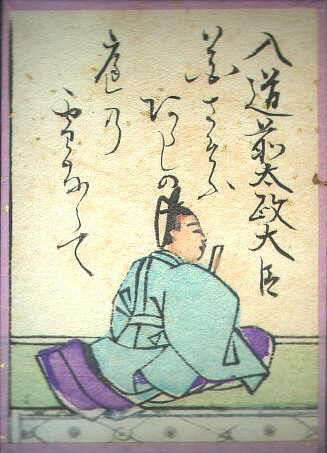
花さそふ あらしの庭の 雪ならで
ふり行ものは 我身なりけり
| はな | |
| 花 | さそふ |
| 名 | 動 |
| ハ四 (連体形) |
| には | |||
| あらし | の | 庭 | の |
| 名 | 格助 | 名 | 格助 |
| ゆき | ||
| 雪 | なら | で |
| 名 | 助動 | 接助 |
| 断定 (未然形) |
打消 |
| ゆ | |||
| ふり | 行く | もの | は |
| 動【掛詞】 | 動 | 名 | 格助 |
| 「降る」(ラ四・連用形) +「古る」(ラ上二・連用形) |
カ四 (連体形) |
主格 |
| わ | み | |||
| 我 | が | 身 | なり | けり |
| 名 | 格助 | 名 | 助動 | 助動 |
| 連体修飾 | 断定 (連用形) |
詠嘆 (終止形) |
桜の花を誘って散らす
嵐が吹く庭の
降り注ぐ桜吹雪ではなく、
年老いてしまったのは
この私なのだなあ。
出典『新勅撰集』雑1・1052
桜の花が舞い散る様子を見て詠んだ歌だ。
「ふる」の掛詞が素晴らしい。 「降る」(舞い散る)桜から、「古る」(老いぼれる)我が身の嘆きへと導いている。
前半は絢爛たる桜吹雪の光景だが、後半では一転して、死を予感させる 雪のような白髪の老人の様子が思い浮かぶ。
作者・入道前太政大臣(西園寺公経)は鎌倉幕府との結びつきも強い公家で、贅沢な暮らしをしていた。
連日贅沢三昧をする中で、ふと老い・死への恐怖を感じたのだろうか。
さて、西園寺公経の歌は、藤原定家の秀歌撰には選び入れられていない。定家は公経をあまり評価していなかったようだ。
にも関わらず、この歌を百人一首に入れたのには、以下の2つの理由があると思われる。
入道前太政大臣(1171 - 1244)
西園寺公経。内大臣・藤原実宗の子。
源頼朝の姪・一条全子を妻としており、鎌倉幕府と密接な関わりを持った。
承久の乱の際は、事前に情報を掴んで幕府に密告。幕府の勝利に貢献し、以降は絶大な権力を持った。
政治的な処世術に長けていたが、それが原因でやっかまれることも多かったようだ。
和歌については、家集もあったが散逸。
『新古今集』以下の勅撰集には114首入集。
 百人一首 (角川ソフィア文庫)
百人一首 (角川ソフィア文庫)