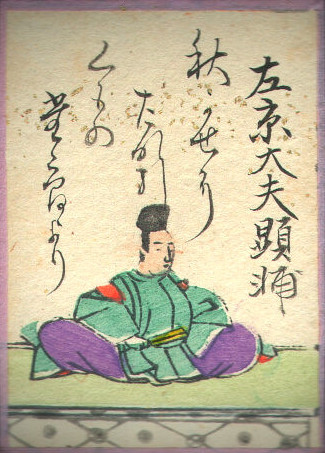
秋風に たなびく雲の たえまより
もれいづる月の かげのさやけき
| あきかぜ | |
| 秋風 | に |
| 名 | 格助 |
| くも | ||
| たなびく | 雲 | の |
| 動 | 名 | 格助 |
| カ四 (連体形) |
| た ま | |
| 絶え間 | より |
| 名 | 格助 |
| も | い | つき | |
| 漏れ | 出づる | 月 | の |
| 動 | 動 | 名 | 格助 |
| ラ下二 (連用形) |
ダ下二 (連体形) |
| かげ | ||
| 影 | の | さやけさ |
| 名 | 格助 | 名 |
| 光。 | 形「さやけし」の名詞化 ※体言止め |
秋風で
たなびいている雲の
途切れ目から
漏れ出てくる月の
光は、澄みきっていることだなあ。
出典『新古今集』秋上・413
秋の月の光を単純に詠み上げただけなのだが、なんとも秋の月夜の清々しさがしんみりと感じられる歌だ。
作者の藤原顕輔は、六条藤家の流派であった。六条藤家の和歌は、『万葉集』を踏まえた考証を基にした理知的な歌風を特徴とする。
しかしこの歌は平明・流麗な調子で実感がこもっており、六条藤家の流派とは幾分違った趣を持っている。
定家はこの点で「秋風に〜」の歌を高く評価していたようだ。
左京大夫顕輔(1090 - 1155)
藤原顕輔。 顕季の三男。
崇徳院の勅命で作成された勅撰集『詞花集』の撰者。
源俊頼とも親交があったようで、その影響を受けている。
『金葉集』以下の勅撰集に84首入集。
 百人一首 (角川ソフィア文庫)
百人一首 (角川ソフィア文庫)