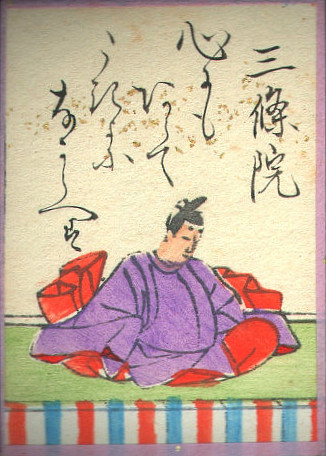
心にも あらで此世に ながらへば
こひしかるべき よはの月かな
| こころ | ||
| 心 | に | も |
| 名 | 助動 | 係助 |
| 断定 (連用形) |
| こ | よ | ||||
| あら | で | 此 | の | 世 | に |
| 動 | 接助 | 代名 | 格助 | 名 | 格助 |
| ラ変 (未然形) |
打消 |
| ながらへ | ば |
| 動 | 接助 |
| ハ下二 (未然形) |
順接 |
| こひ | |
| 恋しかる | べき |
| 形シク | 助動 |
| (連体形) | 推量 (連体形) |
| よは | つき | ||
| 夜半 | の | 月 | かな |
| 名 | 格助 | 名 | 終助 |
| 詠嘆 |
本心ではなく
この世に
生きながらえるならば、
恋しく思うであろう
夜半の月だなあ。
出典『後拾遺集』雑1・860
詞書には
例ならずおはしまして位など去らむとおぼしめしける頃、月の明かりけるをご覧じて
<現代語訳>
病気になって、天皇を退位しようとお思いになっていた頃、月が明るかったのをご覧になって
とある。
三条天皇は1011年に36歳で即位したが、内裏が火災で焼失。1015年に再建したが、それもまた焼失した。
当時、政治的に力をつけていた藤原道長から退位を迫られ、さらに眼病(緑内障か)にもかかり、散々な状況のときに詠まれた。
目を悪くしている中で、月がどのぐらい見えたのかは定かでないが、月を眺めることで現実逃避をしていたようだ。
三条天皇は歌人としてもあまり有名ではなく、この歌は最初はそれほど注目されてはいなかった。
道長の圧力で退位したという歴史的背景もあり、その悲しみ・厭世観が現れたこの歌が百人一首に選ばれたのだろう。
三条院(976 - 1017)
冷泉天皇の第二皇子。 第67代天皇。
986年、11歳の時に立太子。 長い皇太子時代を経て、1011年に36歳で即位した。
眼病・藤原道長からの圧力のため、1016年に当時4歳の東宮敦成親王(一条天皇)に譲位した。
1017年4月に出家。同年5月に42歳で崩御。法名は金剛浄。
勅撰集には『後拾遺集』以下8首入集。 歌集はない。
 百人一首 (角川ソフィア文庫)
百人一首 (角川ソフィア文庫)