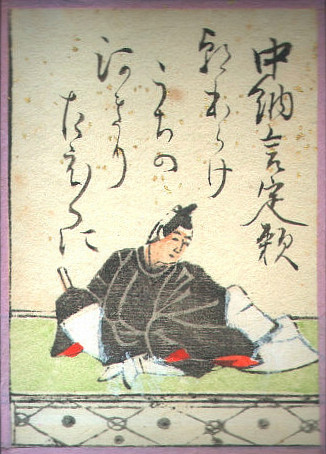
朝ぼらけ 宇治のかはぎり たえだえに
あらはれわたる 瀬々の網代木
| あさ |
| 朝ぼらけ |
| 名 |
| 夜がほのぼの明けた頃。 (「あけぼの」の少し後) |
| うぢ | かはぎり | |
| 宇治 | の | 川霧 |
| 名 | 格助 | 名 |
| 宇治川。 琵琶湖から淀川に注ぐ。 |
| た だ |
| 絶え絶えに |
| 形動ナリ |
| (連用形) |
| あらはれ | わたる |
| 動 | 補動 |
| ラ下二 (連用形) |
一面に…する。 ラ四 (連体形) |
| せぜ | あじろぎ | |
| 瀬々 | の | 網代木 |
| 名 | 格助 | 名 【体言止め】 |
| 魚を捕る網を 仕掛けるための杭。 |
明け方に
宇治川の霧が
途切れ途切れになって、
一面に現れてきた
川瀬の網代木だなあ。
出典『千載集』冬・419
説明無用な叙景歌。
冬の早朝、夜闇と川霧が晴れてきて「網代木」が途切れ途切れ見えてきた、すがすがしい景色が思い浮かぶ歌だ。
この歌が詠まれた当初は、あまりにも単純な歌なのでほとんど評価されなかった。
ところが時代が下ってムードを重視するようになってきた平安後期以降、徐々にこの歌の良さを見直す動きが強まった。
権中納言定頼(995 - 1045)
藤原定頼。 藤原公任の子。
父も有名な歌人だが定頼も典型的な貴族歌人で、歌・書・踊経などの名手だった。
小式部内侍・大弐三位・相模などと親しくしていたようである。
『後拾遺集』以下、勅撰集に45首入集。
 百人一首 (角川ソフィア文庫)
百人一首 (角川ソフィア文庫)