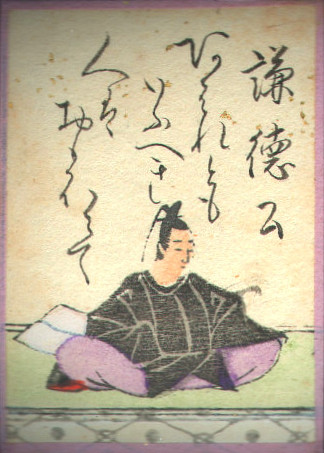
哀れとも いふべき人は おもほえで
みのいたづらに なりぬべき哉
| あは | ||
| 哀れ | と | も |
| 感 | 格助 | 係助 |
| 感嘆、悲哀 |
| い | ひと | ||
| 言ふ | べき | 人 | は |
| 動 | 助動 | 名 | 係助 |
| ハ四 (終止形) |
当然 (連体形) |
| おも | |
| 思ほえ | で |
| 【連語】 | 接助 |
| ハ四動詞「思ふ」(未然形) +自発の助動詞「ゆ」 の連語「思はゆ」(未然形)の転訛 |
打消 |
| み | いたづ | |
| 身 | の | 徒らに |
| 名 | 格助 | 形動ナリ |
| 主格 | (連用形) |
| な | |||
| 成り | ぬ | べき | かな |
| 動 | 助動 | 助動 | 終助 |
| ラ四 (連用形) |
完了・強意 (終止形) |
推量 (連体形) |
感動 |
私のことを哀れだと
言ってくれるはずの人は
思い出されなくて、
私の命はむなしいものに
なってしまいそうだなあ。
出典『拾遺集』恋5・950
詞書には 「ものいひ侍りける女の、のちにつれなく侍りて、さらにあはず侍りければ」 とある。
現代語訳すると 「愛し合っていた女が、段々つれなくなってしまい、しまいには逢わなくなってしまったので」 ということ。
女からフラれてられてしまった、孤独な男の悲しみを切なく詠んでいる。
謙徳公(生前の名は 藤原伊尹)が、自身を主人公(倉橋豊蔭)に見立てて作った物語『一条摂政御集』の出だしの歌である。
謙徳公(924-972)
生前の名は藤原伊尹。 「謙徳公」は死後の諡。
九条右大臣師輔の長男で、貞信公の孫。
和歌の才能にも容貌にも優れているという評判であった。色々な女性との贈答歌を残し、『後撰集』の撰者ともなった。勅撰和歌集には37首入集。
 百人一首 (角川ソフィア文庫)
百人一首 (角川ソフィア文庫)