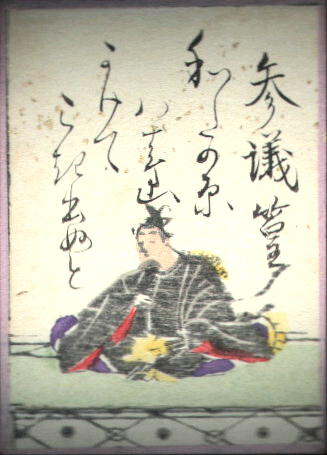
わたのはら 八十嶋かけて 漕出ぬと
人にはつげよ あまのつりぶね
| わたのはら |
| 名 |
| 【海の原】 |
| やそしま | ||
| 八十嶋 | かけ | て |
| 名 | 動 | 接助 |
| カ下二 (連用形) |
| こ | い | ||
| 漕(ぎ) | 出(で) | ぬ | と |
| 動 | 動 | 助動 | 格助 |
| ガ上二 (連用形) |
ダ下二 (連用形) |
完了 (終止形) |
| ひと | つ | ||
| 人 | に | は | 告げよ |
| 名 | 格助 | 係助 | 動 |
| 対象 | 限定・強調 | ガ下二 (命令形) |
| あま | の | つりぶね |
| 名 | 格助 | 名 |
| 【海人】 | 【釣り舟】 |
広々とした海原
はるかの多くの島々に心を寄せて
今船をこぎ出したと
京の都にいるあの人にだけは告げておくれ
釣り人の船よ。
出典『古今和歌集』羈旅・407
参議篁が隠岐の島へ流罪となり船出をしたとき、 はるかな海原への船旅を前にして、故郷の都を思いやった歌である。
流罪になった理由は、遣唐使としての乗船を拒否し、遣唐使を揶揄する漢詩を作ったために、嵯峨上皇の怒りを買ってしまったことだった。
流罪の船出の割には清々しい調子の歌で、悲壮感はあまり感じられない。
釣り人に呼びかける形になっていることで、孤独の余情が効果的に表現されているといえるだろう。
参議 篁 (802-852)
小野篁。小野小町の祖父ともされるが、資料が少なく真偽は不明。
当時漢詩で名高かった岑守の息子。岑守とともに赴いた陸奥で過ごした幼時は弓馬を好み、帰京後もあまり学問をしなかった。これを嵯峨天皇に嘆かれ、学問に転じた。漢詩文で名をあげ、多くの伝説を残した人物。
 飛天闘神譚―異伝・小野篁
飛天闘神譚―異伝・小野篁