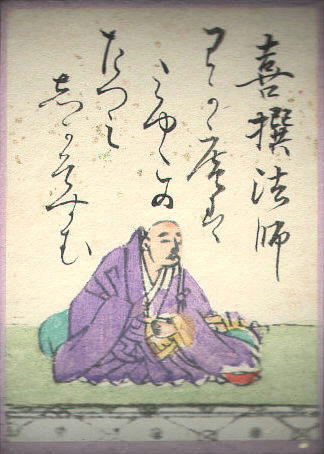
我庵は 都のたつみ しかぞすむ
世をうぢ山と 人はいふ也
| わ | いほ | ||
| 我 | (が) | 庵 | は |
| 代名 | 格助 | 名 | 係助 |
| 所有 | 主体 |
| みやこ | ||
| 都 | の | たつみ |
| 名 | 格助 | 名 |
| 【巽】(南東) |
| しか | ぞ | すむ |
| 【掛詞】 | 係助 | 動 |
| 副「然か」 +名「鹿」 |
「ぞ」の結び(連体形) |
| よ | やま | ||
| 世 | を | うぢ山 | と |
| 名 | 格助 | 【掛詞】 | 格助 |
| 名「宇治山」 +形「憂し」 |
| ひと | なり | ||
| 人 | は | いふ | 也 |
| 名 | 係助 | 動 | 助動 |
| ハ四 (終止形) |
伝聞推定 (終止形) |
私の庵は
都の南東にある。
このように鹿が住むような所に暮らしている。
憂き山、宇治山だと
世の人々は言っているそうだ。
出典『古今和歌集』雑下・983
もともとは、喜撰法師が自分の住処を言葉遊びで自己紹介した歌だった。
ところが『源氏物語』が大流行してから、『宇治十帖』によって宇治=「憂き」場所というイメージが定着し、「世をうぢ山」という表現は、「『源氏物語』から世の人が憂いを感じるあの宇治山」、というニュアンスに変容してしまった。
さらに「然か」+「鹿」を掛詞として解釈することで、鹿の悲しげな鳴き声が聞こえる山里というイメージが被さるようになった。
喜撰法師(生没不詳)
六歌仙の一人として有名だが、この歌以外には確実に喜撰法師と分かっている歌がない。伝未詳。
 百人一首の研究
百人一首の研究