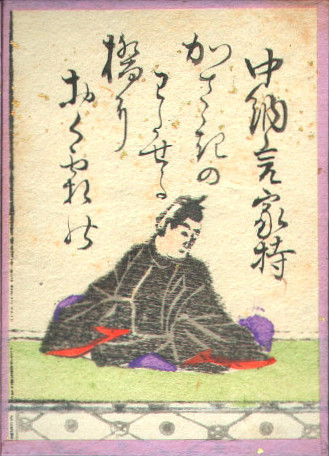
かさゝぎの わたせる橋に をくしもの
しろきをみれば 夜ぞふけにける
| かささぎ | の |
| 名 | 格助 |
| 主格 |
| はし | |||
| わたせ | る | 橋 | に |
| 動 | 助動 | 名 | 格助 |
| サ四 (已然形) |
存続 (連体形) |
| を | しも | |
| 置く | 霜 | の |
| 動 | 名 | 格助 |
| カ四 (連体形) |
| しろ | み | ||
| 白き | を | 見れ | ば |
| 形ク | 格助 | 動 | 係助 |
| (連体形) | マ上一 (已然形) |
| よ | ||||
| 夜 | ぞ | ふけ | に | ける |
| 名 | 係助 | 動 | 助動 | 助動 |
| 強意 | カ下二 (連用形) |
完了 (連用形) |
詠嘆 「ぞ」の結び(連体形) |
鵲が
(翼を連ねて)渡した橋(=天の川に渡したという伝説の橋)に
霜が降りたように
(天の川が)白くなっているのを見ると
夜もすっかり更けてしまったことだなあ。
出典『新古今和歌集』冬・620
この歌は、実は大伴家持の作かどうかは怪しい。
藤原公任が『三十六人撰』を選ぶに当たって、『万葉集』から家持歌をピックアップしているが、その中に入っていないのである。
また、『万葉集』の時代には「鵲」が詠まれた例は無く、平安時代以降に登場し始める。
「鵲の橋」というのは、中国の七夕伝説を踏まえたものだ。
鵲が翼を並べて天の川に橋を架けて、彦星を渡らせるという。
中納言家持(718?-785)
大伴家持。政治的には様々な暗殺・乱の計画に関わったとされ、不遇な扱いを受けた。
 大伴家持 (平凡社ライブラリー)
大伴家持 (平凡社ライブラリー)