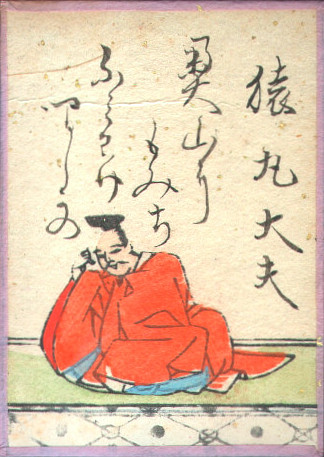
おくやまに 紅葉踏分 なく鹿の
声きくときぞ あきは悲しき
| おくやま | に |
| 名 | 格助 |
| 【奥山】 |
| もみぢ | ふみ | わけ |
| 紅葉 | 踏(み) | 分(け) |
| 名 | 動 | 動 |
| マ四 (連用形) |
カ下二 (連用形) |
| しか | ||
| なく | 鹿 | の |
| 動 | 名 | 格助 |
| カ四 (連体形) |
| こゑ | |||
| 声 | きく | とき | ぞ |
| 名 | 動 | 名 | 係助 |
| カ四 (連体形) |
強意 |
| かな | ||
| あき | は | 悲しき |
| 名 | 格助 | 形シク |
| 【秋】 | 係助「ぞ」の結び (連体形) |
奥山に
(散った)紅葉を踏分けて
鳴く鹿の
声を聞くとき、じつに
秋は悲しいと深く感じることだ。
出典『古今和歌集』秋上・215
紅葉の中で鹿の鳴き声に妻恋いのイメージが重なり、自然と秋の悲しさへとイメージが移ってゆく。
新古今時代に好まれたほのかな艶っぽさ・哀感といった作風がよく現れた作品である。
猿丸大夫(生没年不詳)
「いつの時代の人物かもよく分からない」(三十六歌仙伝)という伝承が残っており、謎の多い人物。
 猿丸大夫は実在した!!―百人一首と猿丸大夫の歴史学
猿丸大夫は実在した!!―百人一首と猿丸大夫の歴史学